
「今日の給食はなにかなぁ~」そんな声が聞こえてきそうです。
今週から新しい年を迎え、ばなな組への進級を意識した活動を行っています。そのひとつが、給食の時間の取り組み①フォークだけで食べる。②自分たちで、おかずをランチョンマットへ運ぶ。 の2点。今までは、スプーンとフォークの2本で食事をしていたので、ちょっぴり食べこぼしが増えたものの、「じょうずでしょ」「ちっくんできた(させた)」と意欲的!それよりも喜んでくれているのが、自分たちでの配膳。同じおかずが乗っているとはいえ、「どれにしようかな~」と迷っている姿がかわいいものです。

あれ?ご飯がふたつも乗っていますが…それもそのはず、ご飯が大好きなお友だちなのです(^^) あれれ??ご飯だけしか乗ってませんが…今日のおかずは見ただけではお気に召さず「いんないの」だそうです(・・;)←結局最後は完食しました! こんなことも毎日のこと!御愛嬌!! 取り組んで1週間にもなると、近くのお友だちが「これ違う」「○○ないよ」と教えてくれたり、子どもたちの順応性にビックリ。もっと早くに取り組んであげていれば…と反省。1歳児でもできることってたくさんあるんだな~と、子どもたちの秘めた可能性に感動してしまいます。
他にも…移行を意識して、ハイハイうんどうの内容を増やしたり、座ったテーブル(グループ)を意識して呼名したり、ロープではなくてお友だちと手をつないで参拝に出掛けたり…ちょっぴりお兄さん・お姉さんの気分で張り切って取り組んでます。
年が明けると、どうしても3月の移行を考えずにはいられず、寂しさがあります… でも!そんなことは言っていられませんよね。来月の生活発表会はもちろん、日々の生活一日一日大切に、楽しく過ごしていきたいと思います。 1歳児クラス担当亜紀子:記


 『からだと心白書』の第2弾をお伝えするはずでしたが、今日はこの八幡宮の拝殿から発信します。
『からだと心白書』の第2弾をお伝えするはずでしたが、今日はこの八幡宮の拝殿から発信します。
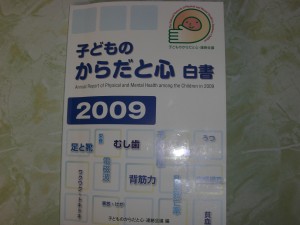
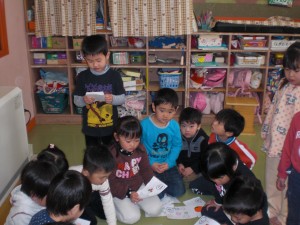
 あけましておめでとうございます。今年も、どうぞよろしくお願い致します。年末、年始の休みも明け、今日から保育園も通常保育になりました。お休みの間、エネルギーのいっぱいたまっていた子ども達は、初日からエンジン全開。寒さなんて何のその、元気いっぱい園庭遊びを楽しんでいます。
あけましておめでとうございます。今年も、どうぞよろしくお願い致します。年末、年始の休みも明け、今日から保育園も通常保育になりました。お休みの間、エネルギーのいっぱいたまっていた子ども達は、初日からエンジン全開。寒さなんて何のその、元気いっぱい園庭遊びを楽しんでいます。