「人間というものは、何か人のために尽くすことによって、大いなる力を得ていくものなのでしょう」
円覚寺館長・横田南嶺さんの言葉です。その館長さんの記事を紹介します。
《とりわけ印象深いのが、盛岡で農業をされているあるご婦人から毎年届く新米です。
ご婦人とは5、6年前、円覚寺の坐禅会に参加してくださったのがご縁でした。
日帰りの会ならともかく、泊まり込みの坐禅会となるとなかなか修行も厳しく、女性の参加は珍しいので
何かご事情でもあるのかと思い、ある時お話をお聞きしたのです。
ご婦人がおっしゃるには、あるスポーツの選手だった息子さんが大きな大会で事故を起こして首の骨を折り、
首から下がほとんど動かない状態になってしまわれた。
絶望した息子さんは、電動車イスで病院の屋上まで上がり、飛び降り自殺を図ろうとしたけれども、
体が思うように動かず思い止まったのだと。
しかし、お話を聞いていて驚きました。
その息子さんはそこから大学に復帰し、さらに一人暮らしを始めたというのです。
ご婦人は「私はあの子が転んでも 絶対に起こしてあげないんです」とおっしゃいました。
体が不自由な子が転べば、すぐにでも手を差し伸べたいのが親というものでしょう。
しかし、ご婦人は自分が先に亡くなった時、息子さんが一人で生きていかなくて
はいけないことを分かっておられたのです。
息子さんにもその思いが伝わったのか、
「自分は母のために生きるんだ。自分が暗くなれば、お母さんがいつまでも 辛い思いをしてしまう。
だから、頑張って生きるんだ」。そう言っていたそうです。
その言葉のとおり、彼は一所懸命勉強して運転免許を取得し、いま地方公務員として立派に自立しておられます。
ご婦人は私にこう言われました。
「管長さん、私はいろいろ苦しんで悲しんで、泣くだけ泣きました。でも私が子供にできることはたった一つ。
一日一日を明るく生きること。それだけです。
もし私が辛い顔をしていたら、息子は母が悲しむのは自分のせいだと自分を責めてしまう。
だからこれからも明るく生きていくの」
もし、お二人が自分のことばかりを考えていたら心は折れていたかもしれません。
しかし、息子さんは母のために生きよう、ご婦人は息子に辛い思いをさせたくないために明るく生きようと、
それぞれに思いを貫いて生きておられます。
人間というものは、何か人のために尽くすことによって、大いなる力を得ていくものなのでしょう。
私は菩提心の発現ともいえる、この母子の姿からそのことを教わる思いでした。》



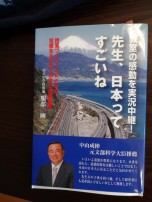


 4月
4月