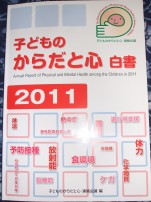 この『子どものからだと白書』が12月に発行されました。毎年、興味のあるところだけでもざっと目を通すようにしています。今回一番に読んだのは、埼玉大学や日体大の先生方で研究された、「運動で脳機能を向上させよう」というタイトルのものです。
この『子どものからだと白書』が12月に発行されました。毎年、興味のあるところだけでもざっと目を通すようにしています。今回一番に読んだのは、埼玉大学や日体大の先生方で研究された、「運動で脳機能を向上させよう」というタイトルのものです。
近年携帯電話やパソコン、携帯ゲーム機等の普及によって、子ども達の体力や運動能力が落ちているのは、誰でも納得いくことだと思います。公園に遊びに行っても、体を動かすのではなく、誰もがゲームに夢中・・・という光景は珍しくなくなっています。
ここでの研究調査は、先ず、15分間の朝活動の時間を利用して行う「運動遊び」前後と「読書」前後の覚醒水準の変化を見たものです。これは、読書では覚醒水準が高まったとは言えない値が示されたのに対して、運動遊びでは覚醒水準が高まった様子を確認できていました。アメリカのイリノイ州のある高校では、一日の始めに朝読書ならぬ「0時間目体育」と呼ばれる身体活動を取り入れたところ、学校全体の成績が著しく向上したという報告があるそうです。(当園の運動プログラムは理想的だと思いませんか?)
覚醒水準が高まれば、当然、別の脳機能にも好影響が及ぶことも予想できるということです。
続いて、運動・読書・ゲームによる短期記憶能力の差異についての調査もありました。これは種々の記号を用意して、忘却個数を比較した結果、運動は0.59±0.89個、読書は0.67±1.18個、ゲームは1.33±1.49個と、運動、読書に比してゲームが忘却しやすい様子を確認できていました。ゲームを行うことが記憶の定着を妨げる可能性を示唆しているようなので、気を付けなければならないと思います。
次に、ゲームをしているときの子どもの脳内酸素量を調べた研究では、ゲームを行っている5分間、一時的に前頭葉の酸素量が減少していたという結果が報告されています。通常、脳が活動するときは、脳内の酸素量が増加すると言われています(以前、成田奈緒子先生が当園の子ども達に行った実験でもその結果は出ていました。)ので、ゲーム中は脳の活動が低下していると言えます。15分でもこのような結果が出るのですから、幼児期からのゲーム使用が長時間続けばどうなるか、おのずと答えが出てくると思います。
さらに、幼少期からの運動実施は、脳への酸素供給や神経伝達物質、さらには神経新生に係わる物資の分泌を引き起こし、正常な脳の発達を保障してくれる可能性さえ教えてくれている。ということで結んでありましたが、週に2~3回程度ジョギングをするグループとしないグループでワーキングメモリテストの成績を比較したところ、実験開始時にはどちらも正解率は65%ということでしたが、3か月ジョギングをしたグループは95%まで上昇、しなかったグループは70%に留まったといいます。
ということで、当園の運動プログラムは月~土の毎日の日課です。幼児期にこのプログラムは絶対にはずせないことを確信しています。私が担当するリンゴ体操ならぬ小集団運動プログラムでは、まず最初に一人一人名前を呼びます。運動前には、少々声や手の上げ方に元気のない子もいます。しかし、運動終了後には(同様に名前を一人一人呼びます)、声も、手の上げ方も、姿勢も、表情もすべて見違えるほどの変化があります。もちろん良くなってです。脳の機能がUPしたと言えるのではないでしょうか。

