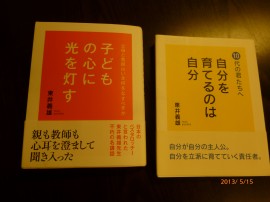今年の伊勢神宮は、20年に一度の式年遷宮の年です。パワースポットでもあるので、若い人達の間でもお伊勢参りの人気は高いようです。その「いせ(伊勢)」というのは、「いもおせ(妹背)」なのだそうです。「いも」は妻、「おせ」は夫のことです。「いもおせ」、それがつまって「いせ」になったといいます。
元伊勢道場長の中山靖雄氏は彼の著『すべては今のためにあったこと』で、次のように書いています。
【私たちは今こうしてここに生まれてきているわけですが、古来ずっと続いてきた夫婦がなければ、生まれることはできませんでした。「いもおせ」つまり、「夫婦」が、命をつなげてきたことで、私たちは今ここに生をうけているのです。
実は、夫婦というものは、お互いの魂を磨くために出会っています。思いがけない心を湧かせ合い、それに気づきお互いが奇麗になっていくというご縁なのです。
夫婦はいっぱい喧嘩して、いっぱい仲直りすればいいのです。喧嘩は何のためにするのかと言ったら、仲良しになる為なのですから。そして喧嘩するたびに近くなっていって、最後は二つでひとつになって天に帰るのです。】
お互いの魂を磨くため…というところが素晴らしいですね。けんかして、仲直りをしようとしても、心のどうにもならない世界があると思います。だからこそ、私たちは心を磨いて修める努力をしていかなければならないと思うのです。