「人生で大切な心構え」として鈴木秀子(文学博士)氏の記事があったので紹介します。
≪人生にはバイオリズムがありますから、波が下降している時は疲れが溜まったり、病気をしたり、
周囲に思わぬ出来事が起きたり、物をなくしたり、大切なことを忘れたり、いろいろなことが起きがちです。
そうすると自分や他人を責めたり、ゴミのような感情が湧き上がってきたりします。
そういう時は無理に自分を変えようとしないこと。
「ああ、いま自分にはこういう 感情が起きているんだな」
とまるで人ごとのように心を静かに眺め、じっと堪え忍びながら上昇の時を待つ訓練をすることです。
そのことに関連した話を最後にご紹介します。
香港に住んでいるインド人の女性が実際に体験した出来事です。
この女性は末期がんに侵され、息も絶え絶えの状態でいわゆる臨死体験をしました。
肉体を離れて自分が寝ている姿を空中から眺め、やがて自分のすべてを受け入れてくれる
温かい光に包まれ、至福感を味わいます。
その時に、自分がなぜがんになったかがはっきりと分かったというのです。
インドはとても競争の激しい社会です。
彼女は自分の正直な心をいつも押し殺して人からよく見られたい、人の上に立ちたい、
出世競争を勝ち抜きたいという思いだけで駆け上がってきていました。
臨死体験をとおして、そういう自分の生き方を振り返るとともに、即物的な生き方がストレスとなり、
ストレスがいつしかがんに形を変えていったことが、理屈抜きに理解できたといいます。
臨死体験後、信じられないようなことが起きました。
彼女の体から奇跡的にがんが消え去っていったのです。
驚いた医者がそれを学会で発表した記録も残っています。
やせ細った体が少しずつ体力を取り戻していよいよ退院となった時、彼女はこれまでのような金儲け主義の生き方、物や地位だけを追い求める生き方を捨て去ろうと固く決意しました。
そして香港に移住。
質素ながら自分らしさを発揮できる仕事を探して、現在はご主人と二人、静かに生活しています。
その彼女がこのように言っています。
「人生で大切なのは、本当に自分らしく生きることと、 何事にも喜び楽しんでいられることです。
あなたが機嫌よくしていさえすれば、それが何よりの社会貢献。
あなたの周りにいる人をみな機嫌よく、気持ちよくできたら、こんな素晴らしいことが他にあるでしょうか」
そして彼女は「そのためには、 いつも正直でいることです」と言葉を続けています。
余計なゴミを取り除いて幸せに生きる秘訣を彼女は自らの体験をとおして私たちに教えてくれているのです。
いつも機嫌よく、しかも自分らしく正直に生きることができたら、心にゴミが溜まることもなくなるでしょう。
自分を機嫌よくするのは自分自身です。
誰かが機嫌よくさせてくれるわけではありません。
これまで外界に向けていたエネルギーを少し自分を機嫌よくするために使ってみてください。
人生はもっと豊かなものになるでしょう。
日々出合う一つひとつの出来事に深い意味があることを知ったら、どんな些細なことも喜びに変わります。
生かされている命の素晴らしさを感じ、喜びが心の内から湧き出る時、私たちは意識せずとも上機嫌で生きられるはずです。≫


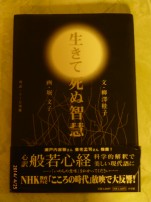 “詩がたり”の 大阪在住の里みちこさんから電話をいただきました。 東京やつくばで、11月と2月に“詩語り会”に呼んでいただいていましたが、夫のことがあって2度ともいけないでいましたが、里さんは「心の出席ね!」と言ってくださっていました。
“詩がたり”の 大阪在住の里みちこさんから電話をいただきました。 東京やつくばで、11月と2月に“詩語り会”に呼んでいただいていましたが、夫のことがあって2度ともいけないでいましたが、里さんは「心の出席ね!」と言ってくださっていました。 毎月2回の設定で、保護者(4名限定)と事務室で昼食を摂っていただく、通称“ドラゴン亭”を実施しています。本日が2回目でした。4月は、新学期が始まったばかりでお母さん方もバタバタしているせいか、申込が少なく、スタッフが前日にあわててお声をかけさせていただく・・・ような状態でした。
毎月2回の設定で、保護者(4名限定)と事務室で昼食を摂っていただく、通称“ドラゴン亭”を実施しています。本日が2回目でした。4月は、新学期が始まったばかりでお母さん方もバタバタしているせいか、申込が少なく、スタッフが前日にあわててお声をかけさせていただく・・・ような状態でした。 本日のお知らせ版にもちょっと登場しましたが、ピエロのおばちゃまについてちょっと紹介を・・・。今から30数年前、何かの集まりでおじちゃんのする手品を見て、子ども達を引き付けられるものはこれだ!と思い、手品の講習会などに出向いていき、グッズを集め始めたのがきっかけです。この衣装は3着目ですが、最初は保護者で裁縫の上手な方が縫って下さったものを長年使っていました。どうせならできるだけ派手に・・と、裁縫は大の苦手ですが、子ども達の為・・となると何でもできるんですねえ。現在のものは、東京へ生地を買いに行き、自分で縫ったものです。自分で縫ったから、ズボンの中には、前にも後ろにも内ポケットがついていて、袖やズボンの裾には、シルクが何枚も隠せるようにゴムをいれてあります。最近は、毎月のお誕生会は全体集会でなくなったので、出番が少ないですが、内容もマンネリにならないよう、数年に1度はグッズを買い付けに行っています。以前は外部からの依頼もあったんですよ。最近では息切れがしてアクティブな動きができなくなってきましたが、子ども達が目を輝かせて見てくれるうちは、自分の楽しみとしても続けたいと思っています。
本日のお知らせ版にもちょっと登場しましたが、ピエロのおばちゃまについてちょっと紹介を・・・。今から30数年前、何かの集まりでおじちゃんのする手品を見て、子ども達を引き付けられるものはこれだ!と思い、手品の講習会などに出向いていき、グッズを集め始めたのがきっかけです。この衣装は3着目ですが、最初は保護者で裁縫の上手な方が縫って下さったものを長年使っていました。どうせならできるだけ派手に・・と、裁縫は大の苦手ですが、子ども達の為・・となると何でもできるんですねえ。現在のものは、東京へ生地を買いに行き、自分で縫ったものです。自分で縫ったから、ズボンの中には、前にも後ろにも内ポケットがついていて、袖やズボンの裾には、シルクが何枚も隠せるようにゴムをいれてあります。最近は、毎月のお誕生会は全体集会でなくなったので、出番が少ないですが、内容もマンネリにならないよう、数年に1度はグッズを買い付けに行っています。以前は外部からの依頼もあったんですよ。最近では息切れがしてアクティブな動きができなくなってきましたが、子ども達が目を輝かせて見てくれるうちは、自分の楽しみとしても続けたいと思っています。