みかん組のお友だち、年末年始元気に過ごせたようですね。保育スタートからニコニコ顔が見られて、嬉しい限りです♪ おもちなどをいっぱい食べたのか、ちょっぴりぽっちゃりして来たお友だちが多いですねぇ~(^v^)

コーナー遊びの時間も、お家の人とゆっくり過ごせた為か、とても落ち着いて遊んでいます。

明日は、もう7日。あっという間に「七草がゆ」を食べる日です。コーナーの時間に、トレイに乗った七草を見せて「これ、葉っぱ食べる?」「人参?違うね。大根ね。」などと言いながら、無病息災を願う七草にまつわるお話しをしました。…が、みんなにはどの位伝わったかな(^^ゞ??

参拝でも、「みんな益々元気に過ごせますように」とお参りしてきました。そして、元気に遊んだ外遊びの後…

一日早く、今日のおやつに七草がゆを「いただきます!」 「おかわりちょうだい」と食べ、今年一年も元気いっぱい過ごせそうですよ!! 1月の保育がスタートすると、みかんさんで過ごせるのも残り3カ月だなぁ…なんてしんみりしてしまいますが、しんみりしていてはもったいない! 一日一日をみんなで楽しく過ごして行こうと心に誓う担任なのでした。 雅子:記
〈おまけ〉参拝前の、ひとコマです。お家では「まだ1歳」「まだまだ2歳」と赤ちゃん扱いされているであろうかわいいみんな。ですが!保育園ではお兄さん・お姉さんになるべく着々と「自分でできた」の喜びを重ねています。きっとお家では”もうちょっとでできるのに”と悔しい思いをしているみんなも、ライバルが近くだとこんなに頑張れるんですね。今日も「できたよ!」の嬉しそうな元気な声が響きました。


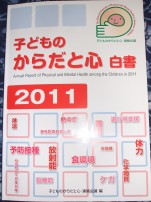 この『子どものからだと白書』が12月に発行されました。毎年、興味のあるところだけでもざっと目を通すようにしています。今回一番に読んだのは、埼玉大学や日体大の先生方で研究された、「運動で脳機能を向上させよう」というタイトルのものです。
この『子どものからだと白書』が12月に発行されました。毎年、興味のあるところだけでもざっと目を通すようにしています。今回一番に読んだのは、埼玉大学や日体大の先生方で研究された、「運動で脳機能を向上させよう」というタイトルのものです。















 玄関の獅子舞
玄関の獅子舞

 学童さんがお掃除を
学童さんがお掃除を

 初夢漬け
初夢漬け