今日のばなな組は、ハイハイうんどう後のおたのしみタイムに、初めて「ぞうきんがけリレー」をしました。
2チームに分かれて行うぞうきんがけリレーは、日頃のぞうきんがけの成果を発揮して、とても白熱した戦いになりました。



見て下さい。腰を高く上げてぞうきんがけをいている姿は、とてもかっこいいですよね★
今日は、初めてのぞうきんがけリレーという事もあってちょっぴり戸惑ってしまう子もいましたが、「がんばれ」 「がんがれ」とみんなで応援しながら2チームとも一生懸命がんばりました。
お部屋もきれいになり一石二鳥のぞうきんがけリレー!!
お家でも、ぜひお子さんと一緒にやってみて下さい。 結構いい運動になりますよ♪ 角野:記

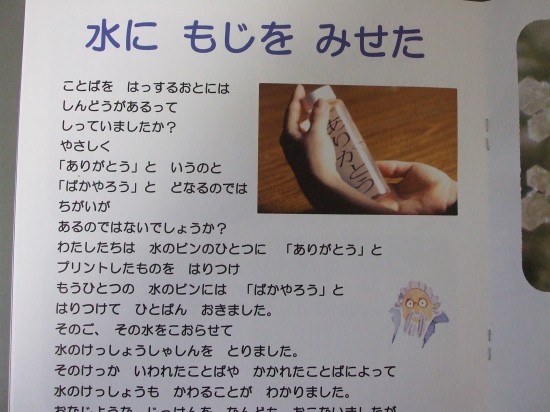
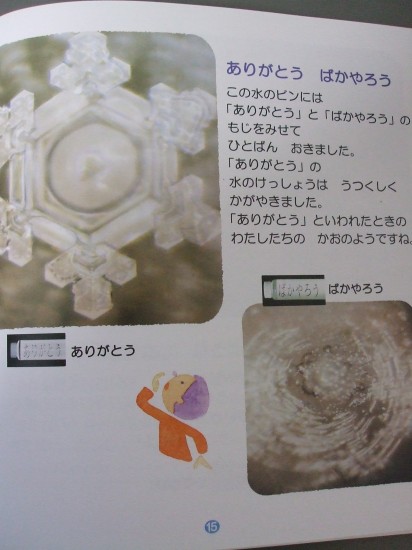






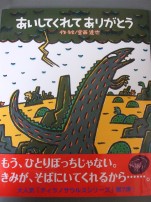
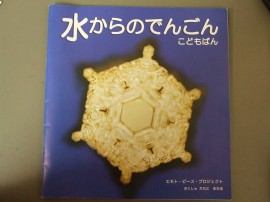 今日のタイトルのように、「愛」とか「ありがとう」は幸せな気分になりますね。
今日のタイトルのように、「愛」とか「ありがとう」は幸せな気分になりますね。












 先々週、敬老の日にちなみ、おじいちゃん、おばあちゃんにお手紙を出しました。郵便局に大事にお手紙を持ってポストに投函してきました。その思い出が残るうちに、園では郵便屋さんごっこをしています。今日の午後は郵便屋さんごっこをしてお手紙を出したりもらったり、とてもほのぼのとした体験をしました。この模様は、後日どこかのクラスでお伝えします。
先々週、敬老の日にちなみ、おじいちゃん、おばあちゃんにお手紙を出しました。郵便局に大事にお手紙を持ってポストに投函してきました。その思い出が残るうちに、園では郵便屋さんごっこをしています。今日の午後は郵便屋さんごっこをしてお手紙を出したりもらったり、とてもほのぼのとした体験をしました。この模様は、後日どこかのクラスでお伝えします。